ここに、明治二六年の測量登山の様子を描いた一枚の絵がある。
そこには、「8月1日導者上条嘉門次ヲ随ヘ雨中明神岳ヲ下ル」というような文字が見える。この絵にある測量師と随行者は、夏とはいえ冷たい雨が落ちる前穂高岳(三、〇九〇m)での調査測量を終え、そこから南に続く明神岳(二、九三一m)の岩場を降りるところである。
案内人(随行者)は、上条嘉門次という地の猟師である。
彼らの下山の様子に注目してみよう。
嘉門次は、背負子状のものを背にして、足には草鞋だろうか、岩場と一体になった安定感のある下山姿が見える。
それに比べて、詰め襟服、脚絆、革靴に洋傘を手にした測量師のそれはどうだろうか。
危なげな姿勢が際立つ。
測量師は、必要な荷のすべてを案内人の背にゆだね、身軽な体にもかかわらず、岩肌に背を向け、コウモリ傘をピッケルにして、いやステッキ代わりにして、無理な姿勢で体重を下へと移動させようとしている。素人目にも、その不安定さが読み取れる。
このスケッチに嘘はない。絵は、測量師当人の手によるものだから。
明治期測量隊のようす
測量師が、何者でどのような業績を上げたのかについてのことは、ひとまず後にして、この絵にあるころの測量について簡単紹介しよう。
明治政府発足の当初は、何事も試行錯誤の様子で組織改変も頻繁に行われたが、時間経過することで次第に落ち着きを見せはじめた。地図測量の関連でも、明治十七年には地図作成の基準となる三角測量が陸軍、後の参謀本部陸地測量部に統一された。その根幹ともいえる一等三角測量も本格化し、明治二六年には件の測量師がこの地域に進入した。
少々わずらわしいのだが、この技術に係わりの少ない読者のために、測量について簡単に説明しておこう。地形図作成と三角測量の係わりのことだが、地形図を作成するには、その基準となる正確な地球上の位置が知られた基準となる三角点といったものが要所に必要になる。ひとことで言ってしまえば、その三角点は一辺と二角を既知として新しい位置を次々と求めていくといったものである。
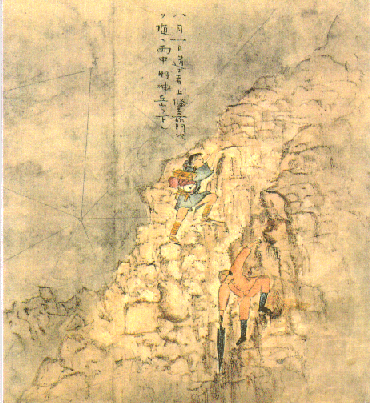
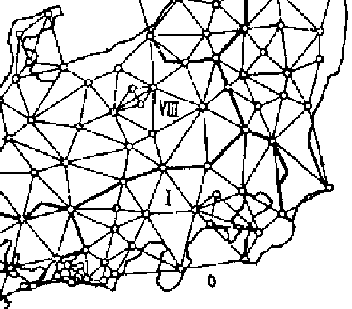
最終的には、五万分の一地形図の整備を目指し、同地形図一枚にほぼ一点の密度で一等三角点を整備する計画となった。同図は、日本全土で約千面、従って一等三角点も約千点の整備が見込まれた(現在の設置数は、九百七十点余)。
その三角測量の工程は、「計画」「選点」「造標」「埋石」「観測」「計算・整理」といった順に実施される。
「選点」は、既存の地図などであらかじめ立てた図上計画に基づいて、三角点の位置を現地で選定することである。点の密度、正三角形にできるだけ近くなるような三角網の形、「視通」と呼ばれる各方向の観測可否の確認、さらに山上での保全などが加味される。
その後、「観測」が行われる。
目標となる櫓を設置し(「造標」)、標石を埋め(「埋石」)、測量標石間で角観測を行い正確な位置を求める。
この絵の測量師は前穂高岳での、この「選点」といわれる作業を終え、まさに下山しようとするところである。
当時は近代的な地図が未整備であったから、図上計画時に利用できる地図も少ない。また、富士山の正確な標高すら明らかでないといった時のことだから、深山の山岳に関する詳細な情報なども得られにくかった。手探り状態での「選点」作業が待っていたと思われる。
ごく少ない現地での情報をたよりに、候補とする峰々を探り、四十、五十キロメートルほど離れた対峙する山岳への視通(線)を確認することになる。その際には、すでに選点を済ませた山頂、これから目指す頂を誤りなく特定することが必要になるが、他所からふらりとやってきた測量師に、これは難しいことであった。
このような不備を、測量師はどのような手段で解消したのだろうか。
そのころ、高山幽谷を熟知していた者といえば、登山講を案内するもの、そして狩猟や採集を生業とするものなどであった。当然のことながら、測量官は不案内な地にあっては、主に後者を現地案内人として助力を得ることとした。
これを裏付けるように、「(測量師には、)穏健なる登山術は必ず山案内人を雇うことにありと教えられます。これ実に山地探検の最善の方法です」、「平人夫は、丈夫でさえあればよろしいが、案内者はその辺の山を永年馳せ回った老猟師に限ります」といった測量師の報告が残されている。
この時も、土地の猟師上条嘉門次が案内人になっている。案内人には、「この尾根の先には、水場があります」、「あの丸みを浴びた尾根の先にある頂が、○○山です」などの適切な助言が求められたであろう。
文字どおり導者の助力を得て「選点」が終り、その頂が三角網を形成するものとしてふさわしいということになれば、仮杭が打ち込まれ、後に観測が行われ、恒久的な標識が設置される。
ところが、剣岳登山で有名な柴崎芳太郎の測量隊は、立山登山の基地であった芦峅寺でガイドを雇おうとして断られた。
その理由については諸説あるが、「古来誰あって登ったという事のない危険山ですから、如何に高い給料を出して遣るからといっても・・・(柴崎報告)」、あるいは「剣岳への道案内できるものはいるが、秘伝として、みだりに人に伝えない。・・・その株を奪われることになるから・・・(日本山岳会、田部報告)」ということであった。
このように、簡単に案内人が確保できないこともあった。
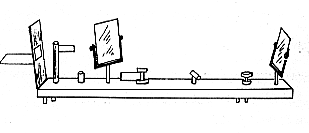
そのほか、測量隊には「測夫」(極めて初期は「常夫」そして、「測夫」、現在は「測手」)と呼ばれる季節雇用の測量助手といったものの存在が重要である。
三角点間の距離が40kmもある一等三角測量では、ヘリオトロープ(回照器)がなくてはならない存在である。周囲の山頂にこれを設置して、時間変化する太陽光を微妙な操作で反射させ、目的方向に信号を送る。この光をたよりに測量官が選点や観測をすることになる。さらに作業の開始や終了を告げる通信手段としての役割も持っていた。
このヘリオトロープの操作を担当する者が、「測夫」である。ただし、彼らの役割はこれだけではない。測量結果を「手簿:観測ノートといったもの」に書き込み、櫓を築き、そして案内人や強力・人夫らの間にあって測量隊をまとめるのも彼らの仕事であり、さらに、永い天幕生活での炊事を含めた雑務一切を取り仕切っていた。
測量の成否を握る重要な役割を、つい今しがたまで彼らが担っていた。
測量隊の装備とコウモリ傘
さて、この測量以前の登山ということだが、古くは修験者が深山、山野を跋渉して修行していた。次いで、登山講が取り入れられて、一般庶民も高山を目指すが、その内情は高山に登ること、いわゆる登山にあるのではなく、そうかといって純粋な信仰でもなく、物見遊山的な意味合いを持ったものであった。
一方、職業人としての山登りはというと、狩猟や薬草の採集を生業とするもの、あるいは国境を警備する見廻り役といった者が担った。江戸後期になると、それらのものに加え、本草学者や文人が高山幽谷を目指すようになる。そして、明治期近く、外国人による科学研究あるいはスポーツ・趣味としての近代登山が行われた。
陸軍の測量師が高山を目指したのは、そうした趣味登山が日本人の中に進行しようとするころ、測量師を含む日本人が、登山という技術を取得する以前のことである。
そのような時期に人跡未踏ともいえる高山を目指した、あの測量官のコウモリ傘は、どのような意味を持っていたのだろうか。
以下前後するが、農商務省山林局が発行した、当時の一般者向けの登山ガイド「登山の心得」(大正五年)には、「背広、詰め襟服、半洋袴を可とす。帯には木綿金巾類、脚絆、ゲートル、靴、草履、杖、洋傘の類、金剛杖、登山杖最も可なり」とある。それ以前、初期山岳会の中心的存在であった木暮理太郎氏の登山姿はというと、和服に脚絆、草鞋履きで背に着茣蓙をまとい、油紙を用意し、荷物を振り分けにして、コウモリ傘を手にしたものだったという(明治二九年)。初期山岳登山者は、概ねこのような装備であった。
ところが、日本山岳会創立者の一人である、小島烏水の「日本山水論」(明治三八年)には、「(コウモリ傘は、)登山には断じて携えて可ならず」とあるが、この絵の時期にはこの助言は生きていない。
小島烏水の声が届いていないのだから、彼の測量師は登山との相性からではなく、和傘に比べたときの有効性から判断して、右手にコウモリ傘が握られたのだろうが、危険極まりない。
日本アルプスを内外に紹介したことで有名なウエストンが、後日穂高岳に向かったときには、測量師と同じように上条嘉門次を案内人とした。もちろん、実績が買われたのである。その時、嘉門次から測量師の下山時の様子を聞き、次のように書き残している。
「政府の官吏(陸軍省の技師)といっしょに登ったが、この役人が最高地点への最初の登頂に成功した。彼は頂上付近の難所で足を滑らせて、岩から岩へ激しくぶつかりながら、ほうり出されるように六十フイートも墜落したが、奇跡的に命拾いをしたそうだ」(「日本アルプスの登山と探検」青木枝朗訳 岩波文庫)。
案の定というか、岩を背にして、右手にコウモリ傘の下山では、危険は避けられなかった。
測量師の当時の心境を、次男による懐古談から聞いてみよう。
「父は全国の山を征服したが、ただ一度命を落としそうな危機に遭った。それは北アルプス穂高で、槍ケ岳の帰途に岩角につまずいて急斜面を滑り落ち、この時ばかりは父も南無阿弥陀仏と唱えたという。事故後には高山の病院に運ばれ、幸い十数日間の入院で全快したが、その時の鮮血に染まった洋服は永く我が家にあった。」
登山技術や装備が不十分な中での初期の測量には、この事件以外にも多くのことが内部研究誌などに残されている。
知床半島の測量では、「天候の急激な変化で天幕に閉じこめられ、三日間も続いた暴風雨によってその天幕も倒され、一時は死を覚悟して(命よりも大事な)『測量手簿』などを残した場所に信号旗を立て、濡れた天幕にくるまったが、五日目にようやく晴れ渡り、シャベルに盛った米を焼いて飢えを癒した」とある。しかも、この測量隊はこの後も測量を続けてから下山した。
深山の滞在では、装備や水・食糧の補給が生死をわけることが多くあった。
このように、明治期測量師は、本来の測量実施以前に多くの困難を克服しなければならなかったそれでも、決して公式の場で弱音を吐くようなことは無かった。その証拠に、今も資料的価値の高い当時の「点の記」(これは後続作業のための覚え、あるいは三角点の戸籍といえるもの)には、彼の測量師も含め苦渋の様子を書き込んだ者は極めて少ない。
生死をも左右することにもなる装備。そのほかのものは、どのようだったのだろうか。登山界では、リュックサックを始めて使用したのは、明治三七年ころといわれ、天幕は明治四二年の夏に初使用したという。
一方で、静岡・山梨県境「毛無山」の「点の記(明治十八年)」には、すでに「天幕を要す・・」とある。

コウモリ傘の測量師
さて、調査登山の絵を描き、前穂高岳を最初に征服したコウモリ傘の測量師の名は、館(舘)潔彦である。
館は、嘉永
二年(一八四九)伊勢国桑名で生まれた。明治元年十九歳のとき桑名から上京、私塾で英学と数学を学んだ。明治
五年に、工部省出仕、当時工部省に招聘されていた英人測量師の下で、東京府下の三角測量に従事した。
その後、陸軍省参謀本部に測量局が設置されるに及んで陸軍技師となり、ここにあるような一等三角測量選点の大半を担当した。
アルプスに来る以前に、東北、四国、中国を巡っていた。このアクシデントの後もわずかな休養の後、北陸、北海道、そして千島の果てまで、日本国中の山野を巡った。登山技術や装備が未熟な時代にあって、未開の山岳地帯での調査測量では、言葉では表せない危険と困難に遭遇したに違いない。
彼を含めた明治期測量隊は、このような環境・装備の下で黙々と、しかも粘り強く激務を進め、山頂に小さな「三角点標石」という証を残した。そして、最終目的である「五万分の一地形図」の全国整備が、三角測量が開始されてから五十年を経た一九二四年にほぼ完了した。
明治大正期を記録したそれぞれの地形図には、名もない測量師の血と汗が含まれている気がする。